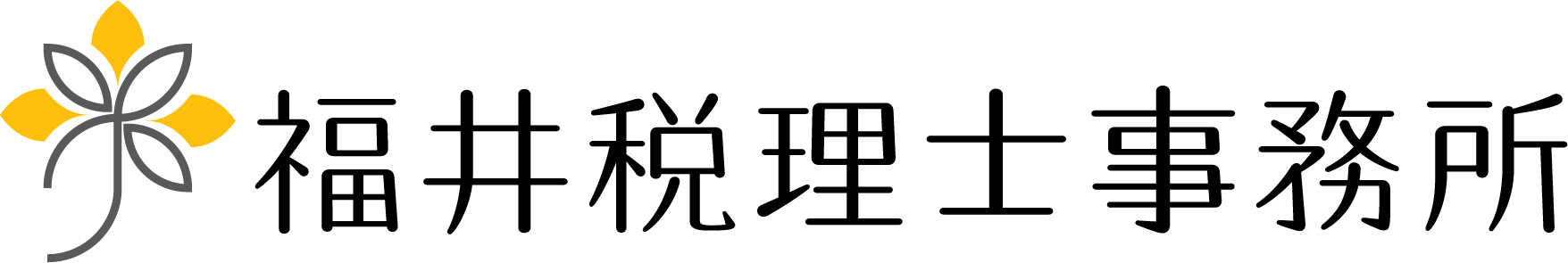事業所得と給与所得の区分 最高裁昭和56年4月24日判決(弁護士顧問料事件)

1.判示事項
本件顧問契約に基づきXが行う業務の態様は、Xが自己の計算と危険において独立して継続的に営む弁護士業務の一態様にすぎないものというべきであり、その業務に基づいて生じた本件顧問料収入は、給与所得ではなく、事業所得に当たると認めるのが相当であるとされた事例。
2.判例要旨
本件顧問料は事業所得にあたる。
3.事案の概要
| ・X(原告・控訴人・上告人)は、自己の法律事務所を営んでいた。 |
| ・Xは、使用人を擁し継続的に弁護士業務を営んでいた。 |
| ・Xは、訴外会社数社とその法律相談に応じる事を内容とする顧問契約を口頭で締結した。 |
| ・各会社は、本件顧問料を弁護士業務に関する報酬に当たるものとして10%の所得税を源泉徴収した上これをXに支払っていた。 |
| ・Xは、確定申告において、これらの報酬を給与所得として申告した。 |
| ・Y税務署長(被告・被控訴人・被上告人)は、これを事業所得として認定し、更正処分をおこなった。 |
4.争点
Xの本件顧問料収入は、事業所得か給与所得か。
5.判旨 上告棄却
①事業所得と給与所得の判断枠組み
およそ業務の遂行ないし労務の提供から生ずる所得が所得税法上の事業所得(同法27条1項、所得税法施行令63条12号)と給与所得(同法28条1項)のいずれに該当するかを判断するに当たっては、租税負担の公平を図るため、所得を事業所得、給与所得等に分類し、その種類に応じた課税を定めている所得税法の趣旨、目的に照らし、その業務ないし労務及び所得の態様等を考察しなければならず、したがって、弁護士の顧問料についても、これを一般的抽象的に事業所得又は給与所得のいずれかに分類すべきものではなく、その顧問業務の具体的態様に応じて、その法的性格を判断しなければならないが、その場合、判断の一応の基準として、両者を次のように区別するのが相当であり、事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、これに対し、給与所得とは雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいい、なお、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない。
②本件への当てはめて
本件事実関係の下においては、本件顧問契約に基づきXが行う業務の態様は、Xが自己の計算と危険において独立して継続的に営む弁護士業務の一態様にすぎないものというべきであり、右業務に基づいて生じた本件顧問料収入は、給与所得ではなく、事業所得に当たると認めるのが相当である。
【参考資料】
民集35巻3号672頁